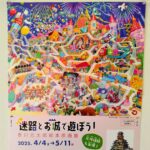私は美術館や博物館に行くのが好きです。
皆さんは、美術館や博物館に足を運ばれたことはありますか?
内閣府による調査によると、一年に一回以上美術館や博物館を訪れた人の割合は42.2%で、訪れなかった人は57.5%だそうです。
また、年齢別にみると、もっとも訪れた比率の高かった世代は60代で、訪れなかった世代は70代とのことです。
この調査結果はもちろん新型コロナウイルスが流行する以前の結果です。
コロナ禍の2020年、展示自体が中止になったり施設が閉館になったりして、美術館を訪れた人の割合はより減ったのではないでしょうか。
約半数の人が一年間で一度も訪れることがない美術館や博物館。
コロナ禍を乗り切った今でも美術館や博物館は展示のあり方や、存続モデルなどを見直していかなければならないと思います。
人はどんなときに美術館や博物館を訪れるのか

先程の内閣府の調査をもう少し細かく見ていきます。
一年間にどのくらいの頻度で美術館・博物館を訪れたかの問いには、訪れた人42.2%の中で「1〜2回」が26.8%、「3〜5回」が11.5%、「6回以上」が3.9%だそうです。
一年のうちで1〜2回訪れる程度の美術館。
そして最も多く訪れているのは60代の方たちです。想像以上に、若年層の利用者や回数が少ないと感じました。
また、どうすれば美術館・博物館にもっと行きやすくなるかの問いに関しては、
「住んでいる地域やその近くに美術館・博物館ができる(増える)」
「入場料が安くなる」
「展覧会の開催に関する情報がわかりやすく提供される」
「全国的あるいは世界的に著名な芸術家の展覧会が開催される」
などが上げられています。
つまり美術館に訪れる人の割合を増やすためには、
✔ アクセスしやすい位置に美術館・博物館がある
✔ 面白そう、あるいは著名な作品の展覧会があるという情報を得やすい
✔ 入場料が安くなる
必要性があるということです。
しかし、本当にそれだけすれば集客力が上がるのでしょうか。
また集客力が低いということは、収益性も低いということです。美術館や、博物館はもともと赤字経営のところが多いと聞きます。
倒産や閉館にならないのは、芸術文化は公益性をかねそなえた事業だからです。
美術館や博物館の名前には必ずと言っていいほど、県や市町村の名前が付いています。(もちろん、個人所蔵、所有の美術館もあります)
公益性や、権威性を保つために金儲けに走ってはならない、というのはもっともな考えだと思います。
多くの著名な美術品を収益の為に売買するのは美術館の役割ではなく画商の仕事だとも思いますし、美術館や博物館は作品や収蔵品の研究調査を行うこともその存在理由のひとつです。
収益目的ではない、でも採算度外視というわけでもないコンテンツ。
それが美術館・博物館における私のイメージです。
美術館・博物館は消費されないコンテンツになり得るか

正直に言えば私も自分にとって興味のない展示の時は美術館・博物館を訪れません。
企画展などは一度訪れれば満足してしまってリピーターになることもないです。
大事なことは、生活圏内や行動圏内に施設があること、そして非日常の場所ではなくなることだと考えます。
それにはやはりアクセスしやすい位置に施設があることや、入館料自体が安く設定されていることも重要だと思います。
何度も自然と利用したくなるような場所であることも大事です。子供の頃から行きなれている場所であれば、大人になっても敷居が高い場所と感じることもなくなるはず。
例えば新たにお店を出したい人向けに期限付きで場所を安く提供したり、コワ―キングスペースとして貸し出したり、もっと自由な施設でいいと思いますがどうでしょうか?
まとめ

収益性重視でもなく、かといって採算度外視というわけでもない。そんなイメージが、美術館や博物館にはあります。赤字になったからといって潰れないから適当でも許される。そんな気持ちで誰も運営はしてないと思います。
私は美術館や博物館でアートに触れる時間が好きです。
自分では到底生み出せないもの、到達できないレベルに触れることが出来る空間が好きです。
芸術や美術は決して敷居が高いものではない。
美術館や博物館を訪れるのがついででも、有名な作品を観るのが主な目的でなくてもいいと思います。
ちょっとすき間時間があるから絵でも眺めたり、美味しい珈琲を飲むついでに素敵な彫刻を見たり・・・でもいいと思います。
もっとアート鑑賞が多くの人にとって身近な娯楽になる時代になれば幸いです。